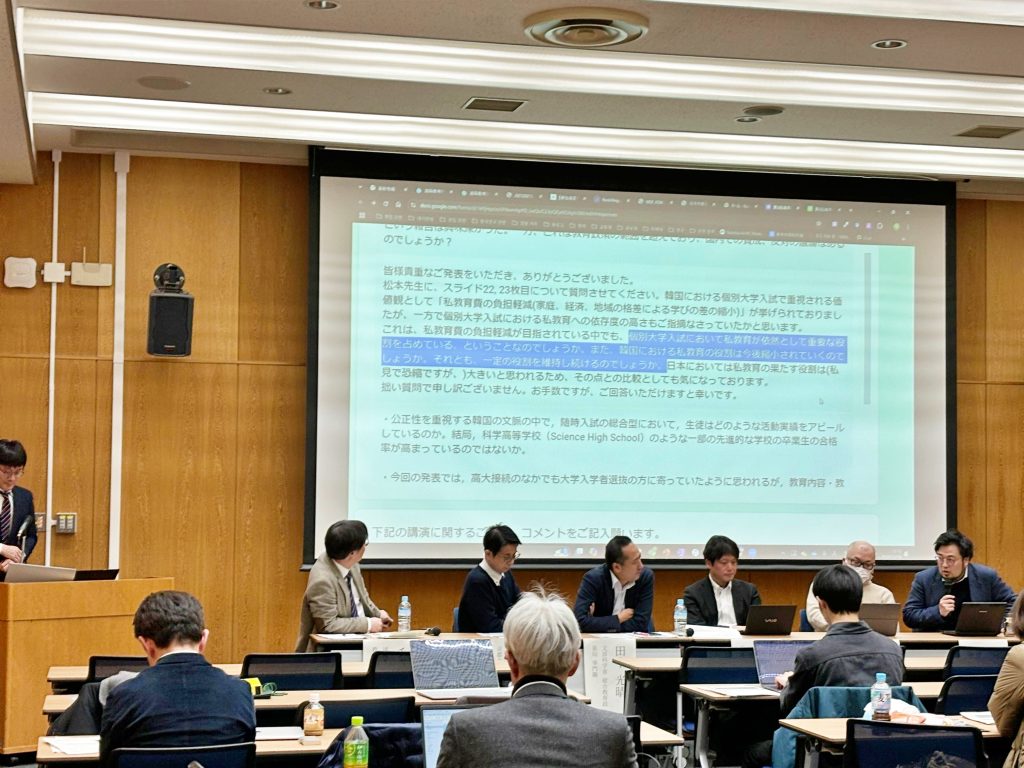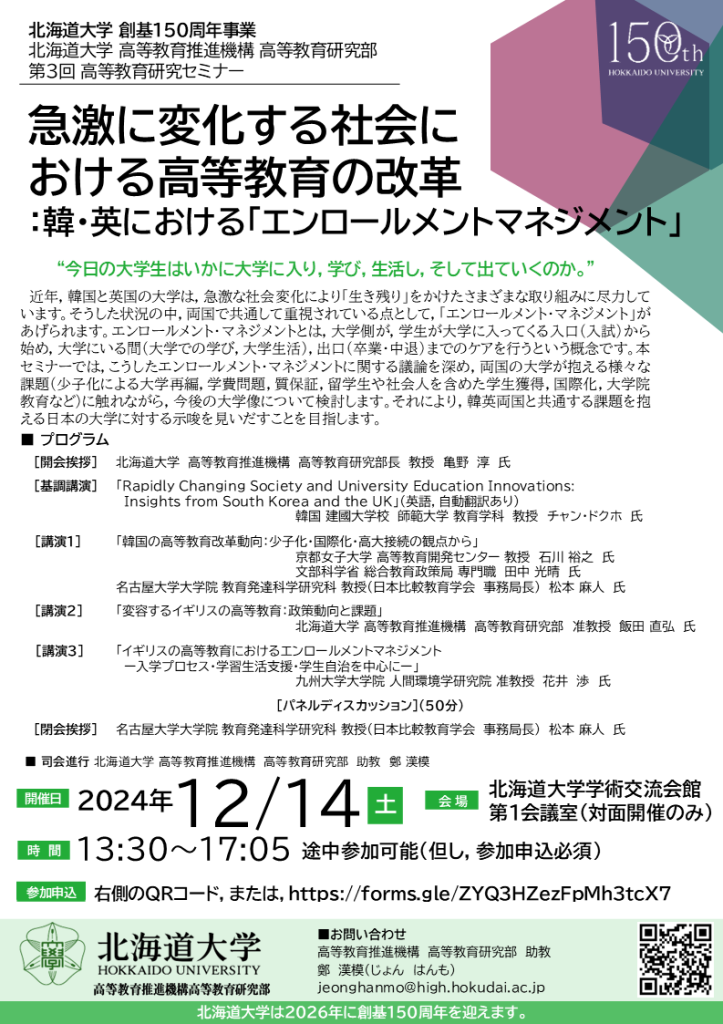活動内容詳細
ACTIVITIES

第3回 高等教育研究セミナー「急激に変化する社会における高等教育の改革:韓・英における『エンロールメントマネジメント』」が開催されました
高等教育研究部 鄭 漢模
実施概要
第3回 高等教育研究セミナー「急激に変化する社会における高等教育の改革:韓・英における『エンロールメントマネジメント』」は真冬の北海道、対面での開催という条件にもかかわらず、遠くは岡山、東京、宮城、近くは道内から、高校生、大学院生、教員、職員など、これからの大学について考えてみたい様々な立場の方々にご参加頂きました(合計:16人)。
各講演内容の要約
今回のセミナーは、まず韓国と英国の大学に関する話をそこから日本への示唆を得るという、多少珍しい内容として企画されました。講師の先生方に関しても、各教育研究機関において韓国、英国に精通する研究者をお招きし、基調講演はチャン・ドクホ先生(韓国・建國大学校)、韓国パートは石川裕之先生(京都女子大学)、田中光晴先生(文部科学省)、松本麻人先生(名古屋大学)、英国パートは飯田直弘先生(北海道大学)、花井渉先生(九州大学)に各々ご担当頂きました。各先生は主に比較教育学会において活動されている先生方で、遠くは韓国、福岡、近くは札幌からお越し頂きました。特に今回のセミナーは、『現代韓国の教育を知る:隣国から未来を学ぶ』(明石書店、2024年3月)の出版を記念し、韓国の高等教育に関してこれまでに蓄積された研究成果をお聞かせ頂く、貴重な場という意味もありました。
チャン先生の基調講演「Rapidly Changing Society and University Education Innovations: Insights from South Korea and the UK」においては、デジタル化(韓国、英国)、少子化(韓国)による急激な社会変化を経験し、さらに、大学に対する財政が縮小されつつある両国から共通点が取り上げられました。チャン先生は、これからの解決方法として、エンロールメント的な目標を国際的なスタンダードに合わせること、大学入学に対する生涯教育モデルの導入、大学行政・教育・研究の改革、IRによる意思決定が求められます。さらに、特に少子化により廃校する大学が続出している韓国の大学に対しては、大学と自治体、大学と国際社会など、大学を取り巻く各ステークホルダーと新しいエコシステムを形成していくことが必要とされます。
次の韓国に関する発表は(題目:「韓国の高等教育改革:少子化、国際化、高大接続の観点から」)、さらに「少子化と地方創生」(石川先生)、「国際化と留学生戦略」(松本先生)、「高大接続」(田中先生)という3つのパートに分かれて行われました。まず、「少子化と地方創生」においては、少子化が首都圏一極集中と地方消滅を促していると同時に、地方大学を消滅の危機に追い込んでいるということで、地方の大学が大学統合再編、寄付金集め、大学ブランディングを通じて生き残る方法を模索している点が取り上げられました。さらに地方の大学を対象にするファンディング(「グローカル30」)や地方の大学と自治体間の連携に基づく新しい財政支援システム(「RISE」)に関するご説明がありました。次に、「国際化と留学生戦略」においては、「5.31教育改革方案」(1995)をきっかけにそれまでの「民族」教育が「グローバル」教育に変化したとし、韓国において大学の国際化が図られ始めました。その後、韓国では留学生数の目標数値として定め着実に努力してきた結果、2023年現在、留学生数は約18万人に達しております。そして韓国政府は、「Study Korea 300k Project」(2023)を掲げ、2027年までに30万人誘致を目標として設定しています。留学生に対する支援を充実しており、入試の改善、留学生支援チューター制度、奨学金、就職支援などが充実化されてきました。一方、留学生の質保証が課題となり、「教育国際化力量評価認証制」、「留学生誘致・管理実態調査」などが導入、実施されています。最後に、「高大接続」に関しては、従来の高校と大学間での接続だけでなく、各学び手と大学間の接続と広く捉え、大学に入学する学生を、高校卒業者、留学生、成人学習者に分けて詳しく説明されました。韓国では、入学後の学生支援が政府による大学評価、大学ランキング(「中央日報大学評価」)の評価項目に含まれているほど重視されています。今後の課題として、人口減少により留学生、成人学習者の受入が増加すると思われる中、これまでに想定していなかった学習者層への対応が必要です。
韓国の次の英国に関する発表は2つの発表に分かれて行われました。うち1つ目の「変容するイギリスの高等教育:政策動向と課題」(飯田先生)は、英国における高等教育政策に関する理解を深める内容で構成されました。2000年代に入ってから、公平性の向上や多様性の確保、低所得層への支援や地域格差の解消を背景に、入学者選抜の改革が行われたことや、学費の上限の引き上げが行われたこと、「全国学生調査」など学生の経験がより重視されるようになったこと、留学生受け入れ政策の緩和などに関する説明がありました。一方で、今後の課題として、所得や地域による教育格差の拡大、大学財政の不安定化、教育におけるデジタル技術の統合、BREXITによるEUからの授業料収入の減少などがあげられました。
2つ目の「イギリスの高等教育におけるエンロールマネジメント-入学プロセス・学習生活支援・学習自治を中心に-」においては、イギリスの高等教育におけるエンロールマネジメントを入学プロセス、学生の学習・生活支援、学生自治制度の3つに分けたうえで各々に関する詳細な説明がありました。まず、入学プロセスの大きな特徴としては、UCAS(The Universities and Colleges Admissions Service)を通じたオンライン出願が行われており、統一システムによる入学プロセスの一元化、簡素化に関する説明がありました。次に、学生の学習・生活支援に関しては、チューター制度を通じた学習支援、学生寮の充実を通じた学生支援を通じた在学生に対するサポートが紹介されました。最後に、学生自治制度に関しては、学生による大学ガバナンスへの参画に関する説明がありました。英国では学生が大学のガバナンスに加わることで、学生自らより良い学習環境を作ることに貢献できるということでした。
各発表へのコメント
セミナー中の参加者からのコメントとして「韓国において留学生政策が国の労働力を確保するためのものとして捉えられていることが興味深い」という意見が寄せられました。韓国において留学生を労働力とみなす観点については、「留学生政策と移民政策間の連携はとれているか」、「留学生政策に対する国内での賛否両論はどうか」という質問がありました。前者に対しては松本先生より「まだそういう動きは見られていない」という回答が、後者に対してはチャン先生より「外国人労働者の活躍がテレビに取り上げられるなど感謝する風潮がある」一方で、「稀に外国人による犯罪が社会問題となり悪化する場合もある」という回答がありました。
また、英国に関しては、「チュートリアルにおいてチューターとして務めるのは教員か、院生か」、また、「チューターの役割は学業に限定されるのか、または、生活やメンタル面にも関わるのか」という質問がありました。前者に対しては、花井先生から「どちらに関しても活動している」という回答がありました。司会者から「教員がチューターを努めることも業績に入るのか」という追加質問に対して、「入らない」ということでした。
さらに、英国に関して、「イギリスの大学へ出願する際には、UCASを活用したオンライン出願で完結し、原本郵送が求められているか」という質問に対して、花井先生から「UCASを通じた出願システムは、イギリスの多くの大学への出願を一元管理するために設計されており、個人情報や学歴、志望する大学やコースの詳細を入力するほか、推薦状や志望理由書(Personal Statement)といった書類をオンラインで提出することが可能」という回答がありました。他にも、「一般的に出願締め切りは1月末ということだったが、その期間までは随時出願を受け付ける仕組みになっているか」に質問に対し、花井先生から「1月31日までに提出してもらうことで、公平に審査される機会が与えられていると思われている」ということで、「大学やコースによってはその後も出願は可能だが、定員や空き状況による制限があるため、情報を早めに確認する必要がある」とのことでした。
事後アンケート調査結果
本セミナー終了後に行われたアンケート調査では(回答者数:7名)、全体的な満足度に関して全員「満足」を選んで頂きました。本セミナーの内容の分かりやすさに関しては「分かりやすかった」6名、「まあ分かりやすかった」1人と、概ね分かりやすかったと思って頂いたことが分かりました。
以下は、自由記述質問項目に対する回答です。まず、今回のセミナーに関する感想です。
- 大変貴重なご講演、ありがとうございました。また今回のように比較教育学に関するセミナーがありましたら是非とも参加させて頂きたく存じます。また、今回は制度的な話についてのご講演がメインでしたので、機会がありましたらぜひ、そういった制度の中で暮らす学生の実感などについて、先生方のご意見を伺いたく存じます。
また、今後取り上げてほしいテーマに関する回答がありました。主にまた違う国について扱ってほしいというのと(1点目)、IRなど大学の質向上に関するより具体的な事例を取り上げてほしい(2点目、3点目)というご意見でした。
- 今後も同様なトピックがあればぜひ参加したいです。日本を入れないところが面白いです。(入れると新鮮味がなく、普通のセミナーになると思います。)韓国やイギリスもいいですが、オーストラリア(NZも含めて)、あるいは最近ホットな台湾留学などもご紹介いただけると嬉しいです。開催頂き、本当にありがとうございました。
- 今後のテーマ希望についてですが、「学生の学びの可視化とそのデータの分析方法」に関わるIRの展開について、各大学の取り組みについて知ることができたらと思っています。
- 具体的にどのようなことをしているのか詳しい内容をお聞きしたかったです。
最後に、課題に関するご指摘もありました。今回のセミナーでは、その場において様々な調整が求められる会場の準備や自動通訳などに対する準備が不十分でした。今後細心の注意を払ってまいりたいと思います。
- zoom翻訳に講演者への同時通訳など、いろいろと高度な作業が求められて、運営が大変だったと思います。
以上、本セミナーに関するご報告でした。ご参加頂いた講師の先生方、参加者の皆様にお礼を申し上げます。ありがとうございました。どうか本年もよろしくお願い致します。